当センター広報紙「NEWS LETTER」No.57 を公開いたしました。
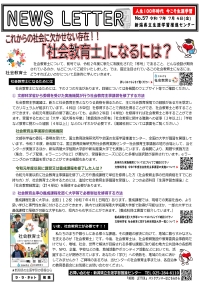
以下のリンクをクリックするとご覧いただけます。
新潟青陵大学短期大学部で、実施を予定している社会教育主事講習(委嘱講習)の定員に空きがあることで、一部の科目について追加募集を行うという連絡がございました。受講までの日程や手続き、受講要件等の詳細につきましては、下の受講案内及びチラシをご確認ください。
なお、夏期に集中的に行われる委託講習につきましては、追加募集はございません。
令和7年度のセンター主催研修会の情報を公開しています。
下のリンクから詳細をご確認ください。
随時、参加申込を受け付けています。
【2019年/DVD/ショートアニメ/36分】ほか
認知症の母みつえと息子ゆういちを中心に、その周りの人たちとの愛情に溢れた介護生活の日々を描いた作品。泣き笑いがある家族の日常と昭和風情溢れる長崎の町並みが重なり、原作の魅力を一層引き立てている。映画版の脚本を担当した阿久根知昭が総監督として起用されている。
【2004 年/DVD/97 分/日本語字幕】
戦後のフランスを舞台に、問題児たちの集まる寄宿舎に赴任した音楽教師が、合唱を通して子どもたちと心を通わせていく姿を描いたヒューマンドラマ。1949 年、フランスの田舎町。失業中の音楽教師マチューは、孤児や問題児が暮らす寄宿舎「池の底」に赴任する。そこには寂しさゆえに心の荒んだ子どもたちと、そんな彼らに体罰を繰り返す校長がおり、学校全体に殺伐とした空気が流れていた。マチューは子どもたちに本来の純粋さを取り戻させるべく、合唱団を結成して歌う喜びを教えようと思いつく。
〈入場料・申込み〉無料・申込み不要
〈定員〉186名 先着順
〈会場〉県立生涯学習推進センター 1階ホール
〈開場〉13:00~(整理券を13:00~、ホールロビーで配布します。)
当センター広報紙「生涯学習Niigata第174号」を発行いたしました。
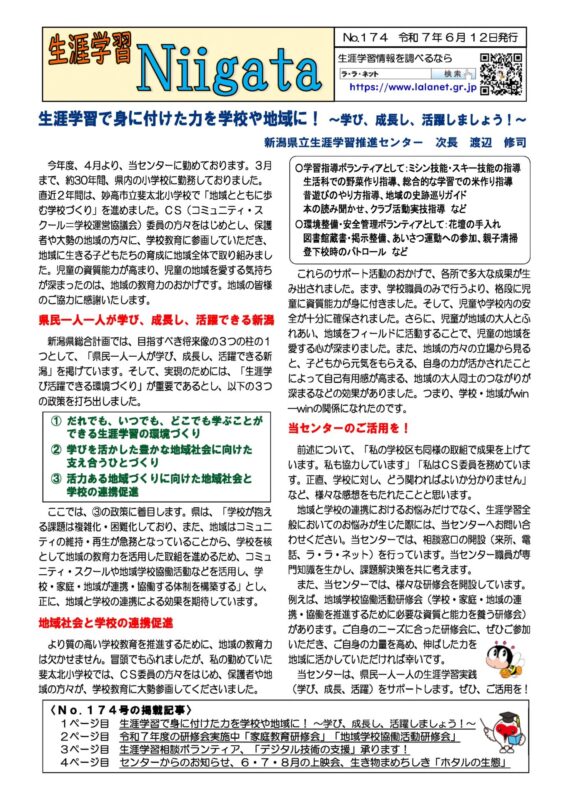
以下のリンクをクリックするとご覧いただけます。
【2016年/DVD/108分】
安倍夜郎の人気コミックを小林薫主演で描いたテレビドラマの映画版「深夜食堂」の続編。路地裏にたたずむ深夜営業の小さな食堂「めしや」を舞台に、個性豊かな客たちが織り成す悲喜こもごもを描く。松重豊、オダギリジョーらドラマ版からのキャストに加え、佐藤浩市、池松壮亮らがゲスト出演。ドラマ版と映画版第1作も手がけた松岡錠司監督が引き続きメガホンをとる。
【1937年/DVD/83分】
魅力的なキャラクター、美しい音と映像と共に誕生した世界初の長編アニメーション。 ディズニーの魔法の伝説の始まり。
美しく心優しい白雪姫。その美しさを妬む継母の女王から命を脅かされ、森の奥深くに逃れた白雪姫は、7人のこびとたち――おとぼけ、ねぼすけ、くしゃみ、てれすけ、ごきげん、先生、おこりんぼ――と出会い、一緒に暮らし始める。ある日、老婆に姿を変えた女王が訪ねて来て、毒リンゴを口にしてしまった白雪姫。横たわる白雪姫の傍らで悲しむこびとたちの元に王子様が現れて…。
〈入場料・申込み〉無料・申込み不要
〈定員〉186名 先着順
〈会場〉県立生涯学習推進センター 1階ホール
〈開場〉13:00~(整理券を13:00~、ホールロビーで配布します。)
ご利用方法などの詳細は新潟県立図書館ホームページをご覧ください。